プロ直伝・在宅ワークスペースを整える3ステップ収納術

在宅ワークが日常となり、自宅のワークスペースが生活の中心になった方も多いのではないでしょうか。
しかし、気がつけばデスクの上が書類やガジェットで散らかり、集中できない、せっかくのおしゃれな部屋が台無しになっているといったお悩みを抱えていませんか。
この記事では、プロが実践する簡単な3つのステップを通じて、機能性と美しさを兼ね備えた理想のワークスペースを実現する方法をご紹介します。
日々の仕事効率を高めながら、心地よい生活空間を保つためのヒントが満載です。
在宅ワークで散らかりがちなデスク周り、こんな悩みはありませんか?
在宅ワークが日常となり、自宅のワークスペースは仕事と生活の拠点として重要な役割を担っています。
しかし、その環境が整理されていないと、集中力の低下やストレスの原因となることがあります。
多くの在宅ワーカーが抱えるデスク周りの悩みは多岐にわたりますが、
特に「仕事道具が生活空間にあふれてしまう」「集中できる環境が作れず、作業効率が上がらない」「おしゃれなインテリアと機能的な収納を両立したい」
といった3つの課題は共通して挙げられることが多いでしょう。
これらの悩みは、単に物が散らかっているという表面的な問題に留まらず、私たちの仕事のパフォーマンスや日々の暮らしの質にも深く関わってきます。
次に、それぞれの悩みを具体的に掘り下げていきましょう。
その1.仕事道具が生活空間にあふれてしまう
在宅ワークの普及に伴い、仕事用の機材や書類が自宅の生活空間に溢れてしまうという悩みを抱えている方は少なくありません。

例えば、ダイニングテーブルが日中は仕事の資料やノートPCで埋め尽くされ、食卓としての機能が果たしにくくなるケースが挙げられます。
このような状況は、単に部屋が片付かないという見た目の問題だけでなく、仕事とプライベートの境界線を曖昧にしてしまうという精神的な側面も持ち合わせています。
また、クライアントとのオンラインミーティング時に、背景に生活感のあふれる物が映り込んでしまい、プロフェッショナルな印象を与えられないといった問題に直面することもあるでしょう。
仕事道具が生活空間に浸食することで、住まいの快適性が損なわれ、日々の暮らしの質にまで影響が及んでしまうのです。
いかにして生活空間の美しさを保ちながら、必要な仕事道具を効率的に収納するかが、在宅ワーカーにとって大きな課題となっています。
その2.集中できる環境が作れず、作業効率が上がらない
整理されていない環境は、集中力や作業効率に大きな影響を与えてしまいます。
デスク周りに多くの物が置かれていると、視覚的な情報過多となり、集中すべきタスクから注意が逸れてしまいがちです。
また、必要なものを探すのに時間がかかることも、作業効率を著しく低下させる要因です。
探し物をするたびに思考が中断され、再びタスクに戻るまでに集中力を再構築する時間が必要になります。

このように、雑然としたデスク環境は、無駄な時間と精神的エネルギーを消費させ、生産性の低下を招いてしまうのです。

例えば、デスクを部屋の隅や壁側に配置することで、視界に入る情報が限定され、集中しやすい環境を作り出すことができます。
また、デスク上の照明だけでなく、部屋全体の明るさも作業に適した状態に調整することも大切です。
このように、物理的な環境を整えることは、テレワークにおける集中力維持と作業効率向上に直結すると言えるでしょう。
その3.おしゃれなインテリアと機能的な収納を両立したい
在宅ワークが主流となる中で、自宅のワークスペースを機能的に整えることはもちろん、インテリアとしての美しさも保ちたいというニーズは高まっています。
しかし、市販されている多くの収納グッズは、機能性を重視するあまりデザイン性が二の次になりがちで、せっかくこだわって選んだ家具や雑貨が並ぶ空間に、プラスチック製の収納ケースを置くことに抵抗を感じる方も少なくありません。
特に、北欧デザインや和モダンといった、素材感やシンプルな美しさを重視するインテリアスタイルを好む方にとっては、部屋の雰囲気を損なわずに収納力を高めることは大きな課題です。
仕事用の書類や文房具、PC周辺機器といった生活感が出やすいアイテムをどのように収納し、いかに部屋全体の調和を保つかという点で頭を悩ませています。
機能性だけでなくデザイン性も兼ね備えた収納ソリューションを見つけることは、在宅ワークの満足度を大きく左右します。
美しく整理された空間は、見た目の快適さだけでなく、精神的なゆとりや集中力の向上にも繋がるため、機能性とデザイン性の両立こそが、理想的なワークスペース作りの鍵となるのです。
改善ステップ1:現状把握から始める「出す・分ける・減らす」整理術
在宅ワークスペースを整える最初のステップは、闇雲に収納アイテムを増やすことではありません。
まずは、今あるものの現状を正確に把握し、「出す・分ける・減らす」という基本の整理術に取り組むことが重要です。
このプロセスは、理想のワークスペースを作り上げるための土台となり、その後の収納計画をスムーズに進めるための不可欠な作業と言えるでしょう。
このステップを丁寧に行うことで、何が必要で何が不要なのかが明確になり、効率的かつ機能的な空間へと生まれ変わらせる準備が整います。
一見、遠回りに思えるかもしれませんが、この現状把握こそが、散らかりにくい快適なワークスペースを実現するための鍵となります。
・デスク周りのものを一度すべて出す
整理の第一歩は、デスク周りにあるものすべてを一度外に出すことです。

これは、普段見過ごしているものや、存在を忘れていたアイテムも含め、自分がどれだけのものを所有しているのかを客観的に把握するために非常に重要なプロセスとなります。
この作業は、ゼロベースで最適な配置を考えるための準備運動とも言えます。
面倒に感じるかもしれませんが、この一手間が、後々の効率的な収納計画へとつながるのです。
この「すべて出す」という行為は、物理的な整理だけでなく、精神的なリセットにも繋がります。
まっさらになったデスクを見ることで、どのようなワークスペースにしたいのか、どのような機能を持たせたいのかをじっくり考える良い機会にもなるでしょう。
・「毎日使う」「時々使う」「使わない」の3つに分類する
デスク周りのものをすべて出し終えたら、次はそれらを「毎日使うもの(一軍)」「時々使うもの(二軍)」「使わないもの(三軍)」の3つに分類しましょう。
この分類作業が、今後の収納計画の基礎となります。
「毎日使うもの(一軍)」には、ノートPC、筆記具、メモ帳、スマートフォンなど、業務中に頻繁に手を伸ばすアイテムが該当します。
これらは、手の届く範囲に配置することで、作業効率が格段に向上します。
「時々使うもの(二軍)」には、参考書籍、予備の文房具、充電器、印鑑など、週に数回程度使うアイテムを分類します。

そして「使わないもの(三軍)」には、過去の書類、壊れたガジェット、もう使わない事務用品などが含まれます。
これらは、すぐに手放すか、別の場所に保管することを検討しましょう。このように明確な基準で分類することで、物の定位置が決まり、探し物の時間がなくなり、片付けもスムーズになります。
・不要なものを手放して、本当に必要なものだけを残す
分類が終わったら、「使わないもの(三軍)」に分類されたアイテムたちをどうするかを決めましょう。
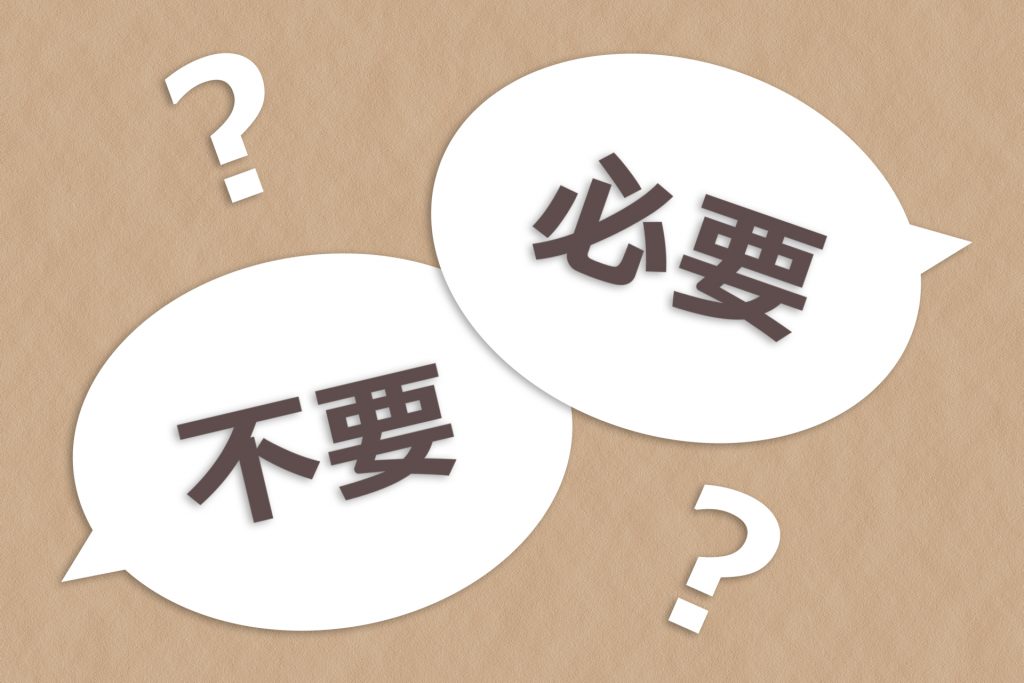
ただ捨てるだけでなく、保管、譲渡、売却、リサイクルといった様々な選択肢があります。

ものを減らすことは、単に物理的なスペースを確保するだけでなく、精神的なゆとりを生み出す効果もあります。
視覚的に情報量が減ることで、集中力を保ちやすくなり、思考がクリアになるというメリットも期待できるでしょう。
このステップを徹底することで、デスク周りはもちろん、心の中もスッキリと整理され、日々の仕事や生活に対する集中力が高まります。
本当に価値のあるものだけに囲まれた空間は、あなたにとって最適な作業環境となるはずです。
改善ステップ2:動線を意識したゾーニングで物の住所を決める
整理術の次の段階では、物の定位置を明確にする「ゾーニング」という考え方を導入します。
これは、ただ物をしまうのではなく、作業の流れを考慮して配置を計画することを意味します。
どこに何があるかがはっきりわかるようになると、必要な物を探す無駄な時間がなくなり、作業の効率が格段に上がります。
また、片付けもスムーズに進むため、いつも整頓された状態を維持しやすくなります。このゾーニングが、より快適なワークスペースを実現するための重要な鍵となるでしょう。
・手の届く範囲には「毎日使う」一軍アイテムを配置
ステップ1で分類した「毎日使う」一軍アイテムは、作業効率を最大限に高めるために、デスクの最も使いやすい場所に配置することが大切です。
具体的には、椅子に座ったまま手を伸ばせば届く範囲に置くようにします。
この範囲は「アームズリーチ」とも呼ばれ、PC、キーボード、マウス、毎日使うペンやノートなどがこれに当たります。例えば、ノートPCを使用する場合、最小限必要なデスクのサイズは幅60cm×奥行40cmが目安です。
この限られたスペースを有効活用するためには、モニターやPC本体の配置を工夫し、その周りに最も頻繁に使うアイテムをレイアウトすることが重要です。
これにより、作業中に立ち上がったり、視線を大きく移動させたりする手間が省け、集中力を途切れさせずにスムーズに作業を進められます。
一軍アイテムの配置は、使用頻度が高いものほど手前や利き手側に置くといったルールを決めることで、さらに効率的な動線が生まれます。
こうした細かな工夫が、日々のテレワークにおけるストレスを軽減し、生産性の向上につながります。
・引き出しや棚には「時々使う」二軍アイテムを収納
ステップ1で「時々使う」と分類された二軍アイテムは、デスクの引き出しや、デスク横に設置するキャビネット、または後述するモニタースタンドの下など、手が届きやすいけれど視界には入りにくい場所に収納するのが最適です。
これにより、デスク上はすっきりと保ちつつ、必要な時にはすぐに取り出せる利便性を両立できます。

例えば、引き出し付きのデスクは、文房具や書類、資料などを整理して収納するのに非常に便利です。
また、デスクの横に置く引き出しタイプの収納は、デスクと同じ高さのものを選ぶと、作業スペースを一時的に拡張する補助デスクとしても活用できるため、限られたスペースを有効活用する工夫としておすすめです。
これらの収納を活用することで、一軍アイテムの配置エリアを侵食することなく、作業に集中できる環境を保てます。
頻度は高くないけれど、いざという時に困らないよう、それぞれのアイテムの「住所」を明確に決めておくことが、片付けやすさと使いやすさにつながるでしょう。
・「見せる収納」と「隠す収納」を使い分けてスッキリした印象に
在宅ワークスペースを機能的かつ美しく整えるためには、「見せる収納」と「隠す収納」を上手に使い分けることが重要です。
インテリアの雰囲気を損なわずに収納力を高めたいという要望に応えるためにも、この使い分けは非常に効果的です。
「見せる収納」には、お気に入りのデザインの文房具、観葉植物、アート作品など、インテリアのアクセントになるようなアイテムを選びましょう。
ただし、見せる収納は物を多く置きすぎると雑然とした印象になるため、厳選したアイテムを配置するよう心がけることが大切です。

引き出しの中や蓋つきの収納ボックス、キャビネットなどを活用して、これらを視界から遮ることで、ワークスペース全体をすっきりと洗練された印象に保てます。
この「見せる」と「隠す」のバランスを意識することで、機能性とデザイン性を両立した、集中できる美しいワークスペースを作り出すことができるでしょう。
改善ステップ3:便利アイテムで収納力とデザイン性を格上げする
基本的な整理が終わった後、さらに一歩進んで、収納力とデザイン性の両方を兼ね備えたワークスペースを作りませんか。
このセクションでは、これまでご紹介した整理術をベースに、より快適で美しい空間を実現するための便利なアイテムをご紹介します。
これらのツールを導入することで、散らかりやすいデスク周りの悩みを解消し、見た目も機能性も格段に向上させることが可能です。
ワークスペースが、より洗練された、集中できる空間へと生まれ変わるヒントを見つけていきましょう。
・デスク上のスペースを縦に活用する(モニタースタンド・卓上棚)
デスク上のスペースは限られているため、横方向だけでなく、縦方向を有効活用することが重要です。
特にモニタースタンドは、ディスプレイの位置を上げることで、自然と背筋が伸び、長時間の作業による肩や首への負担を軽減する効果が期待できます。
また、モニタースタンドの下には、ノートパソコンを収納したり、キーボードやマウスを使わない時に隠したりするスペースが生まれます。
これにより、デスクを広く使うことができ、必要な書類や小物を置く場所を確保できます。さらに、ペン立てや小物入れを置けば、頻繁に使うアイテムを手の届く範囲にスマートに収納できます。
卓上棚も同様に、書類やファイル、文房具などを複数段に分けて収納できるため、縦の空間を最大限に活用し、デスク上をすっきりと保つ効果的なアイテムです。
・ごちゃつく配線を隠して足元スッキリ(ケーブルボックス・天板裏収納)
在宅ワークスペースの美観を損ねる大きな要因の一つが、パソコンや周辺機器から伸びる複雑な配線ではないでしょうか。
絡み合ったコードは見た目が悪いだけでなく、掃除の妨げにもなり、不慮の事故につながる可能性もあります。この配線問題を解決するために、ケーブルボックスや天板裏収納といったアイテムが非常に役立ちます。

ケーブルボックスは、電源タップや余分なケーブルをまとめて収納できる箱型のアイテムです。これにより、床に散らばりがちなコード類を一つにまとめ、ホコリの蓄積を防ぎながら見た目をすっきりとさせることができます。
また、デスクの天板裏に取り付けるバスケットやトレーも効果的です。これらは電源タップやACアダプター、ケーブルなどをデスクの視界に入らない位置に固定できるため、足元が格段に広がり、掃除もしやすくなります。
使用する機器の数や配線の量に合わせて、最適な収納方法を選び、快適なワークスペースを実現しましょう。
・壁面を有効活用して収納スペースを増やす(有孔ボード・ウォールシェルフ)
デスク周りだけでは収納が足りない場合や、床面積を有効活用したい場合には、壁面収納が非常に効果的です。
特におすすめなのが「有孔ボード」です。有孔ボードは等間隔に穴が開いている板で、フックや棚、ボックスなどを自由に組み合わせて取り付けることができます。
これにより、収納する物の形やサイズに合わせてレイアウトを自在に変更でき、文房具、メモ、タブレットなどを「見せる収納」としてディスプレイしながら整理できます。
また、ウォールシェルフも壁面収納の強力な味方です。

お気に入りの本やグリーン、写真立てなどを飾ることで、殺風景になりがちな壁をおしゃれなインテリアの一部に変えることができます。
ウォールシェルフは、収納だけでなく、空間に奥行きと彩りを与える効果も期待できるため、機能性とデザイン性を両立したい方にはぴったりのアイテムです。
まとめ
この記事では、在宅ワークスペースを整える3つのステップを紹介しました。
まず「出す・分ける・減らす」で必要なものを厳選し、次に「動線を意識したゾーニング」で使いやすく配置。
最後に「便利アイテム」で収納力とデザイン性を高めれば、快適で機能的な空間が完成します。
整理された環境は集中力と効率を高め、仕事の質を向上させるだけでなく、オンオフの切り替えもスムーズに。
お気に入りの空間で、仕事も暮らしも充実させましょう。




