今すぐできる!クローゼット整理術!-簡単3ステップをご紹介-
クローゼットや押し入れが物であふれかえり、毎日の服選びに時間がかかったり、探しているものが見つからなかったりといった経験はありませんか。
片付けたい気持ちはあるものの、何から手をつければ良いのか分からず、つい後回しにしてしまう、そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、単に物を減らすだけでなく、心にもゆとりをもたらす「断捨離」の考え方に基づいた、クローゼットや押し入れの具体的な整理術をご紹介します。
誰でも実践できるステップを通して、効率的な収納方法から、リバウンドを防ぐための習慣作りまで、網羅的に解説しています。
この記事を読み終える頃には、きっとすっきりとした空間で、快適な暮らしを実現するための第一歩を踏み出せるはずです。

1.クローゼットが物であふれて片付かない…その悩み、この記事で解決します

物が多すぎて片付けが追いつかない、限られた収納スペースをどう活用すれば良いかわからない、あるいは「何を捨てていいのか」の判断に迷ってしまうなど、クローゼットや押し入れに関するお悩みは尽きないものです。
特に、狭いアパートでの生活では、これらの問題は日々のストレスに直結してしまいますよね。
もう諦めてしまっている方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
この記事は、そんなお悩みを抱える方のために作成した、クローゼット整理の完全ガイドです。
整理前の準備から、具体的な断捨離の実践方法、効率的な収納術、そして美しい状態をキープするための習慣作りまで、ステップバイステップで徹底的に解説しています。
この記事でご紹介する具体的な方法を実践することで、散らかったクローゼットが、理想とするすっきりとした空間へと変わっていくことでしょう。
読み進めていただくことで、「片付けられない」という長年の苦痛から解放され、快適な毎日を送るためのヒントが見つかるはずです。
さあ、一緒にクローゼット整理の旅を始めてみませんか。
2.なぜクローゼット整理が必要?断捨離がもたらす嬉しいメリット
クローゼットの整理は、単に物を物理的に減らすことだけが目的ではありません。
不要な物を手放し、物への執着から解放されることで、心の中も整理されていくという考え方、それが「断捨離」です。断捨離は、快適な空間を得ることはもちろん、私たちの生活全体に様々な嬉しい変化をもたらしてくれます。
まず、物理的なメリットとしては、家事が格段に楽になることが挙げられます。物が少なくなれば、掃除の手間が減り、探し物をする時間も短縮されます。
これにより、時間的な余裕が生まれて、これまで片付けに費やしていたエネルギーを趣味や家族との時間に使えるようになるでしょう。
また、収納スペースが確保されることで、新たに購入するものを厳選するようになり、無駄な買い物が減るため、お金が貯まりやすくなるという効果も期待できます。
さらに、断捨離は精神面にも良い影響を与えます。不要な物を手放すプロセスを通じて、自分にとって本当に大切なものは何か、何が必要で何が不要なのかという「自分の価値観」に気づくきっかけになります。
これは、自己理解を深め、より充実した人生を送る上で非常に重要な要素です。物が少ないシンプルな生活は、選択肢を減らし、日々の決断疲れを軽減する効果もあります。
心にゆとりが生まれることで、人間関係も良好になるなど、多くのポジティブな変化が生まれる可能性があります。
このように、クローゼットの整理は、単に「捨てる」こと自体が目的ではなく、その先に待っている快適な空間と、心に余裕のある豊かな暮らしを手に入れるための大切な一歩なのです。
3.【ステップ1】準備編:整理をスムーズに進めるための事前準備

断捨離を成功させるためには、やみくもに作業を始めるのではなく、事前の準備がとても大切です。
この後のセクションで詳しくお伝えする「理想のイメージ作り」「必要な道具の準備」「まとまった時間の確保」という3つの準備をしっかりと行うことで、作業が格段にスムーズに進み、途中で挫折することなく最後までやり遂げられるでしょう。
理想のクローゼットをイメージする

断捨離を始める前に、まずは「どんなクローゼットにしたいか」そして「すっきりした部屋でどのような生活を送りたいか」を具体的にイメージすることが重要です。
たとえば、「毎朝、服を選ぶのが楽しくなるようなクローゼット」や「趣味のキャンプ道具がすぐに取り出せる押し入れ」など、具体的なシーンを思い描いてみてください。
この「理想のイメージ」は、あなたが物を手放すかどうかの判断基準となり、途中で迷いが生じた際の大きな道しるべになります。
理想を具体的に描くことで、単に物を減らすことだけが目的ではなく、「快適な暮らしを手に入れる」という本来の目的を常に意識できるようになります。
この明確な目標が、断捨離のモチベーションを維持し、最終的な成功へと導く原動力となるのです。
必要な道具を揃えよう
整理作業を効率的に進めるためには、事前にいくつかの道具を準備しておくと良いでしょう。最低限用意しておきたいのは、「必要」「不要」「保留」のカテゴリーに分けるためのダンボール箱が数個と、不要な物を処分するための大きくて丈夫なゴミ袋です。
これらをあらかじめ用意しておくことで、仕分け作業が滞りなく進められます。
さらに、クローゼットの中の物をすべて出したタイミングで、内部をきれいに清掃できるように、掃除機や雑巾なども手元に用意しておくことをおすすめします。
物が何もない状態で掃除をすれば、普段手の届かない場所までしっかりきれいにでき、よりすっきりとした気持ちで収納を始められますよ。
整理する時間を確保する
断捨離は、中途半端に始めてしまうとかえって部屋が散らかる原因になりがちです。そのため、集中して「一気に徹底的に行う」ことが成功の秘訣となります。
週末の午前中など、他の予定を入れずに、断捨離だけに集中できるまとまった時間を事前に確保しましょう。
特に、思考がクリアで判断力が高い「朝の時間」から作業を始めるのが効果的です。他のことに気を取られず、整理だけに集中できる環境を整えることが、スムーズな断捨離を成功させるための大切な一歩となります。
4.【ステップ2】実践編:迷わない!クローゼット・押し入れの断捨離手順
いよいよ、クローゼットや押し入れの断捨離、実践編です。ここでは「全部出す」「仕分ける」「保留にしたアイテムの期限決め」という3つのステップで、具体的な作業を進めていきましょう。
この手順に沿って進めることで、物が多すぎて何から手をつけていいか分からない、何を捨てるべきか判断できないといった悩みを解消し、迷うことなくスムーズに整理を進めることができますよ。
ぜひ、ここからの内容を参考に、快適な空間を手に入れるための第一歩を踏み出してくださいね。
1. まずは全部出す!持ち物を把握しよう
断捨離の最初のステップは、クローゼットや押し入れの中身を「全部出す」ことです。この作業は一見大変に思えるかもしれませんが、実は最も重要なポイントの一つなんですよ。
全ての物を一度外に出すことで、自分がどれくらいの量の物を持っているのかを視覚的に把握することができます。
普段は扉の奥に隠れていて見えない物がどれほどあるのか、意外な発見があるかもしれませんね。なぜ全部出すことが大切なのでしょうか。
それは、隠れている物も含めて、一つひとつの物とじっくり向き合う覚悟を決めるためです。奥にしまい込まれて存在すら忘れていた物も、外に出すことで「こんな物もあったな」と気づき、改めて必要かどうかを判断する機会が生まれます。
この「全部出す」という行動自体が、物への執着を手放し、整理を進めるための心の準備になるのです。
大変な作業ではありますが、ここを乗り越えれば、断捨離はもう成功したも同然。頑張って一歩を踏み出してみましょう。
2.「必要」「不要」「保留」の3つに仕分ける
クローゼットや押し入れから全ての物を出したら、次はそれらを「必要」「不要」「保留」の3つのカテゴリーに仕分けていきます。
この分類は、断捨離のプロセスをシンプルにし、判断に迷う時間を減らすために非常に効果的な方法です。それぞれのカテゴリーが何を指すのかを明確にしておきましょう。
「必要」な物は、今現在使っていて、これからも使い続けるであろう物です。例えば、頻繁に着る洋服や、日常的に使う家電製品などがこれにあたります。
「不要」な物は、劣化・破損している物、長期間使っておらず今後も使う予定のない物、そして買い直せる物など、手放しても困らない物です。
そして「保留」は、必要か不要かの判断に迷う物、つまり「もしかしたら使うかも」「まだ使えるから」といった理由で手放す決断ができない物が入ります。
このシンプルな3分類を活用することで、仕分け作業が格段に進めやすくなりますよ。
迷わないための仕分け基準
「必要」「不要」「保留」の3つに仕分ける際に、最も頭を悩ませるのが「何を捨てるべきか」という判断ですよね。
そんな時に役立つ具体的な判断基準をいくつかご紹介します。これらの基準を参考に、ご自身の心と物の声に耳を傾けてみてください。
まず、大切なのは「ときめくかどうか」という感覚です。これは、その物を見た時に心がウキウキしたり、喜びを感じたりするかどうか、という自分の気持ちに問いかける基準です。
もし心がときめかないのであれば、それは今のあなたにとって必要のない物かもしれません。
次に、「1~2年以内に使ったか、あるいは使う予定があるか」も重要な判断基準です。多くの専門家が「1年以上使っていない物は今後も使う可能性が低い」と指摘しています。
特に衣服は、季節を一周して一度も袖を通さなかった場合は、手放すことを検討してみましょう。
また、「今の自分に似合うか、必要か」という視点も忘れてはいけません。以前は気に入っていたけれど、今のライフスタイルや好みに合わなくなった服やアクセサリーはありませんか?
人は常に変化していくものですから、物もそれに合わせて見直すことが大切です。そして、「買い直せるかどうか」という基準も有効です。
もし手放してもすぐに手に入る物であれば、無理に取っておく必要はないかもしれませんね。これらの基準を複合的に使うことで、迷う時間を減らし、スムーズに仕分けを進めることができるでしょう。
【注意】断捨離で捨ててはいけないものリスト
断捨離を進める中で、つい勢い余って大切なものまで捨ててしまわないよう、いくつか「捨ててはいけないもの」をご紹介します。
後で後悔することのないように、このリストを参考に注意しながら作業を進めてくださいね。まず、契約書、年金手帳、保険証券、免許証などの「重要書類」は絶対に手放してはいけません。
これらは再発行に手間がかかったり、場合によっては再発行が不可能だったりするものもあります。次に、写真や手紙、賞状など「二度と手に入らない思い出の品」も慎重に扱ってください。
これらはデジタル化するなどの工夫で物理的な量を減らすことはできますが、完全に手放す前に一度じっくり考える時間を取りましょう。
また、非常食や防災グッズなど「緊急時に必要なもの」は、いざという時の命綱となるため、必ず手元に残しておくべきです。
そして、家族や同居人の物など「自分以外の所有物」は、必ず本人に確認を取ってから判断してください。
勝手に処分するとトラブルの原因になってしまいますので、特に注意が必要です。
3.「保留」にしたアイテムの期限を決める
「必要」「不要」に分類できたものの、「保留」に仕分けたアイテムの扱いは、断捨離の次のハードルになることが多いですよね。
この「保留」ボックスがいつまでも部屋の片隅に置かれたまま、結局はまた物が増えてしまう…という経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
そうならないために、保留にしたアイテムには「期限」を設定することが非常に大切です。まずは、保留にした物をまとめて収納する「保留ボックス」を用意しましょう。
ダンボール箱などでも構いません。そして、そのボックスに「3ヶ月後」「半年後」といった具体的な見直し日を記した付箋を貼ってください。この期限が来たら、再びボックスの中身を取り出して、もう一度「必要かどうか」を判断します。
期限が来るまでの間に一度も使わなかった物や、存在すら忘れていた物であれば、今度こそ感謝の気持ちとともに手放す決断ができるはずです。
どうしても手放せない高価な物や、かさばる季節用品などで、物理的な収納スペースに困る場合は、トランクルームの活用も検討してみると良いでしょう。
アイテム別!断捨離のコツ
クローゼットや押し入れの中には、衣類だけでなく、本や雑誌、小物、アクセサリーなど、さまざまな種類の物が収納されていますよね。
それぞれのアイテムには、特有の判断基準や整理のポイントがあります。ここからは、代表的なアイテム別に、効率的に断捨離を進めるためのコツを具体的にご紹介していきます。
ご自身の持ち物と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてみてください。
衣服:1年以上着ていない服から手放す

衣類の断捨離は、クローゼット整理の中でも特にボリュームがあり、判断に迷いやすい項目かもしれません。最も分かりやすい基準は、「1年以上着ていない服から手放す」ことです。
日本の四季を一周して一度も袖を通さなかった服は、来年も着る可能性は低いと考えられます。思い切って手放すことで、クローゼットに新しい風を吹き込みましょう。
他にも、サイズが合わなくなった服、シミや黄ばみ、型崩れがあるなど劣化している服、そして今の自分の趣味やライフスタイルに合わない服も手放す候補です。
高かったから、まだ一度しか着ていないから、という理由で手放すのをためらってしまうこともあるかもしれませんが、「今後本当に着るのか?」と自問自答してみてください。
もし着ない服でクローゼットがパンパンになっていると、本当に着たい服が埋もれてしまい、毎日の服選びが憂鬱になってしまいます。
手放すことで、本当に気に入った服だけが残り、ファッションを心から楽しめるようになりますよ。
本・雑誌:読み返すかどうかで判断
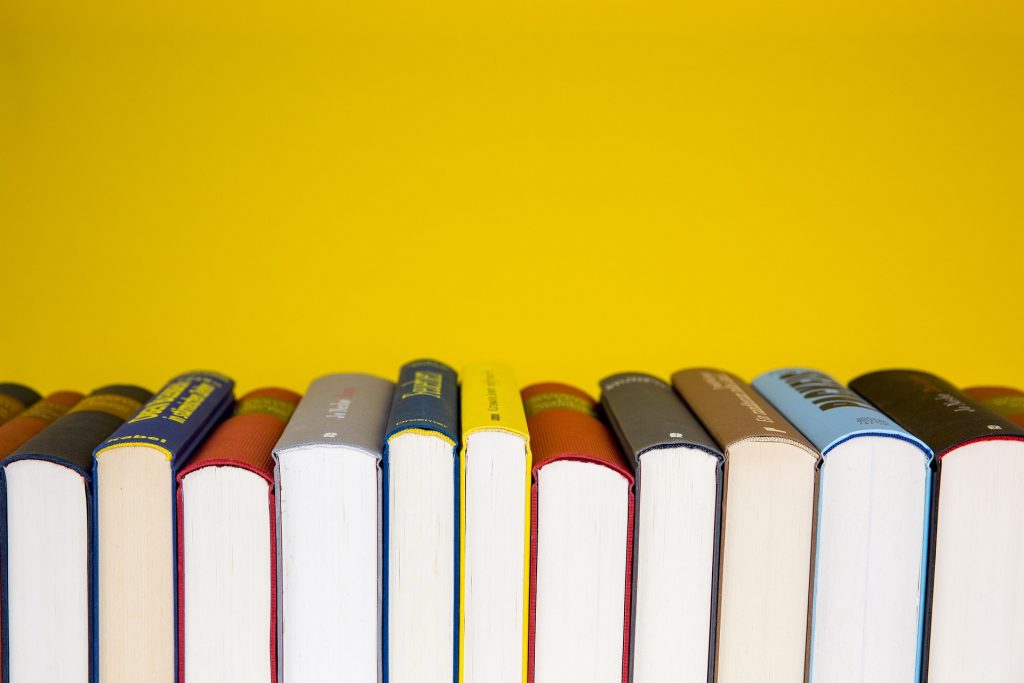
本や雑誌は、気がつくと棚にぎっしり詰まってしまい、かなりのスペースを占拠していることがありますよね。
これらを断捨離する際のコツは、「今後、本当に読み返すかどうか」を判断基準にすることです。一度読んだビジネス書や小説、情報が古くなってしまった雑誌などは、意外と読み返す機会が少ないものです。
例えば、過去のトレンド情報が載っているファッション誌や、一度解き終えた問題集、情報が古くなってしまったハウツー本などは、手放しても困らない場合が多いでしょう。
もし、どうしても手放せないけれど、物理的なスペースを取りたくないという場合は、専門業者に依頼して電子書籍化(自炊)したり、必要なページだけをスキャンしてデータとして保存したりする方法も有効です。
本当に価値のある情報や、何度も読み返したい愛読書だけを手元に残すことで、本棚も心もすっきりしますよ。
小物・アクセサリー:壊れているものや使っていないもの

小物やアクセサリー、メイク用品、バッグなどは、細々としていてついつい後回しにしてしまいがちですが、これも断捨離の対象です。一つひとつは小さくても、たくさん集まると収納スペースを圧迫してしまいます。
それぞれのアイテムに合った判断基準で整理していきましょう。
例えば、アクセサリーなら、壊れているもの、錆びているもの、片方しかないピアスは思い切って手放しましょう。
今の手持ちの服に合わないものや、使う機会がほとんどないフォーマルなアクセサリーなども、よく考えてみてください。メイク用品は、未開封で約3年、開封後は約半年が使用期限の目安とされています。
古くなったものや肌に合わなくなったものは処分し、新しいものを取り入れるスペースを確保しましょう。
バッグやポーチ類も、持ち手が傷んでいるもの、型崩れしているもの、流行遅れで使わなくなったものは手放す候補です。
このように、明確な基準を持つことで、後回しにしがちな小物類も効率よく整理できますよ。
5.【ステップ3】収納編:リバウンドしない!使いやすいクローゼットを作るテクニック
断捨離でクローゼットや押し入れの物が減っただけでは、またすぐに散らかってしまうという「リバウンド」を経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
せっかく時間と労力をかけて整理した空間をきれいに保つためには、「使いやすく、戻しやすい収納」を作ることが何よりも大切です。
このセクションでは、一度きれいにしたクローゼットや押し入れの状態を維持するための基本ルールと、収納をさらに快適にするための便利なグッズ活用法を詳しくご紹介します。
これらのテクニックを取り入れることで、いつもすっきりとした、心地よい空間を保てるようになりますよ。
収納の基本ルール3つ
使いやすいクローゼットを実現するには、いくつかの基本的なルールがあります。
これからご紹介する「使用頻度別の定位置管理」「立てる収納」「7割収納」という3つのルールを意識するだけで、どなたでも格段に使いやすい収納システムを構築できるようになります。
ルール1:使用頻度別に定位置を決める
物の収納で最も大切なことの一つは、全ての物に「住所」を決めてあげることです。特にクローゼットや押し入れでは、使用頻度に合わせて物の定位置を決めることが、使いやすさの鍵となります。
よく使う一軍の洋服やバッグは、目線の高さから腰の高さまでの「ゴールデンゾーン」と呼ばれる最もアクセスしやすい場所に配置しましょう。
一方、季節外れの衣類、年に数回しか使わない冠婚葬祭用の小物、思い出の品など、使用頻度の低い物は、天袋やクローゼットの最下段、押し入れの奥といった、多少取り出しにくい場所を定位置とします。
このようにゾーニングすることで、必要なものがすぐに見つかり、探す無駄な時間がなくなり、片付けも格段に楽になります。
ルール2:「立てる収納」で取り出しやすく
収納スペースを有効活用し、物をスムーズに取り出せるようにするテクニックが「立てる収納」です。
Tシャツ、靴下、下着、タオルなどを重ねて収納するのではなく、畳んで立てて並べることで、引き出しや収納ケースを開けた時に何がどこにあるか一目瞭然になります。
重ねてしまうと下にあるものが取り出しにくく、結果的に収納全体が乱れがちですが、立てる収納であれば、必要なものだけをサッと取り出せ、他の物が崩れる心配もありません。
本や書類も、平積みするのではなくブックエンドなどを活用して立てて並べることで、目的のものを素早く見つけられるようになります。
ルール3:余白を残す「7割収納」を意識
収納スペースは、パンパンに詰め込むのではなく、少し「余白」を残すのが美しく快適な状態をキープする秘訣です。
この「7割収納」という考え方は、収納容量の2~3割を空けておくことで、物の出し入れがしやすくなり、結果的に散らかりにくくなるというものです。
例えば、引き出しの7割に衣類を収め、残りの3割は空けておきます。
収納にゆとりがあると、新しい物を一時的に置くスペースができたり、物の出し入れの際にスムーズに動かせたりと、日々の使い勝手が格段に向上します。
見た目にも心にも余裕が生まれ、完璧を目指しすぎないことが、きれいな状態を長続きさせる秘訣となるでしょう。
整理がはかどる!おすすめ収納グッズ活用術
世の中には数多くの収納グッズがありますが、その中からクローゼットや押し入れの整理に特に役立つアイテムを厳選してご紹介します。
このセクションでご紹介する「折りたたみコンテナ」や「中身が透けない引き出しケース」は、単に物をしまうだけでなく、整理効率も高めてくれる優れものです。
これらのグッズを上手に活用して、より快適な収納スペースを実現しましょう。
使わない時は隙間に収納「折りたたみコンテナ」
使わない時はコンパクトにたためる「折りたたみコンテナ」は、限られた収納スペースを最大限に活用するための強い味方です。
必要な時にパッと広げて使い、不要な時は厚さわずか7cmに折りたためるので、クローゼットの隙間やベッドの下、車のトランクなど、ちょっとしたスペースにもすっきりと収納できます。
もともと物流現場で使われている業務用コンテナがベースになっているため、頑丈さも抜群です。積載荷重は10kgあり、最大5段まで積み重ねて使えるため、季節ものの衣類やかさばるアウトドア用品、食料品のストックなど、様々な物の収納に適しています。
フタや仕切りがない分、自由な使い方ができるのも魅力です。
さらに、グレー、ベージュ、ホワイト、ライトブルーといった落ち着いたカラーバリエーションが豊富なので、お部屋の雰囲気やインテリアに合わせて選べます。
機能性とデザイン性を兼ね備えた折りたたみコンテナは、収納の悩みを解決し、快適な空間作りに貢献してくれることでしょう。
折りたたみコンテナ両扉
見た目すっきり「中身が透けない引き出しケース」
クローゼットや押し入れを開けたときに、中身が見えない収納ケースは、生活感を消して空間全体をすっきりと見せる効果があります。
特に、色や形がバラバラな小物類を収納する際に「中身が透けない引き出しケース」を活用すると、統一感のある美しい収納空間を作り出すことができます。
S・M・Lと異なるサイズ展開がある場合でも、奥行きが統一されている製品を選べば、複数組み合わせても段差なくきれいにスタッキング(積み重ね)できるのが特徴です。
例えば、文房具やハンドタオルにはSサイズ、衣類にはMやLサイズと使い分けることができます。
引き出しにはストッパー機能が付いているので、勢いよく開けても抜け落ちる心配がなく、安心です。
また、別売りのキャスターを取り付ければ、掃除の際やレイアウト変更の際にも簡単に移動できるため、使い勝手がさらに向上します。
アイボリー、グレー、くすみピンクなど、落ち着いたおしゃれなカラーが多いのも魅力です。
中身が見えないことで、細々とした物を気にせず収納でき、見た目の美しさを保ちながら、整理整頓を快適に進められるでしょう。
スタックシステムケース
ラベル活用で自分だけのオリジナル収納を作る

収納グッズを活用して物を定位置に収めたら、最後の仕上げとして「ラベリング」をすることで、さらに使いやすく、リバウンドしにくい収納が完成します。
特に、中身が透けない引き出しケースやコンテナを利用した場合、何が入っているのか一目でわかるようにラベリングすることは必須です。
家族みんなが物の場所を把握できるようになるため、使った後も元の場所に戻しやすくなります。
ラベリングの方法は様々です。手書きのシンプルなラベルから、テプラのような専用のラベルライターで作成したおしゃれなラベル、さらには衣類のアイコンシールなどを活用するのも良いでしょう。
「トップス」「シーズンオフ小物」「防災グッズ」のように具体的に記載することで、探す手間が省けます。自分好みにカスタムすることで、整理収納への愛着が深まり、きれいな状態を維持するモチベーションにもつながります。
6.きれいなクローゼットをキープする3つの習慣
断捨離で物を減らし、収納を整えた後も、そのきれいな状態を維持することはとても大切です。
残念ながら、一度片付けても、日々の暮らしの中で意識しなければ、物はまた増え、クローゼットが散らかってしまうことは少なくありません。
でもご安心ください。これからご紹介する3つの簡単な習慣を毎日の生活に取り入れるだけで、リバウンドを防ぎ、常に快適なクローゼットをキープできるようになります。
定期的に見直す日を作る
クローゼットのきれいな状態を維持する一つ目の習慣は、「定期的な見直し」をスケジュールに組み込むことです。
衣替えのタイミングや、季節の変わり目、あるいは年末の大掃除など、年間で数回、「クローゼットを見直す日」をあらかじめ決めておくと良いでしょう。
この見直しの日に、クローゼットの中にある持ち物全体を軽くチェックしてみてください。
その時に、もう着なくなった服や、流行遅れの小物、破損しているものなど、不要になったものがないかを確認します。
また、収納場所が今の生活スタイルに合っているか、より使いやすい配置はないかを見直すことで、物が溜まりすぎるのを未然に防ぎ、大掛かりな片付けが不要になります。
日々の小さな見直しが、常に整ったクローゼットを保つ秘訣です。
2.「1つ買ったら1つ手放す」を徹底する
物の総量を増やさないための鉄則として、「1つ買ったら1つ手放す」ルールを徹底するのも、きれいなクローゼットを維持するための大切な習慣です。
例えば、新しいトップスを購入したら、今あるトップスの中から一番古くなったものや、あまり着ていないものを一つ手放すというシンプルなルールです。
このルールを徹底することで、物理的な物の量が常に一定に保たれ、収納スペースが溢れるのを防ぐことができます。
また、新しい物を買うたびに「何を手放そうか」と考える癖がつくため、本当に必要なものなのかを深く考えるようになり、衝動買いの抑制にも繋がります。
この習慣は、クローゼットだけでなく、家全体の物を管理する上でも非常に効果的ですよ。
3. 使ったら必ず元の場所に戻す
きれいな状態を維持するための最も基本的で、かつ非常に重要な習慣は、「使ったら必ず元の場所に戻す」ことです。
クローゼットを片付けた時に決めた、それぞれの物の「定位置」に、使った物をすぐに戻すことを意識してみてください。
「後でやろう」が、部屋が散らかる一番の原因になりがちです。着替えた後の服を椅子にかけっぱなしにしたり、帰宅後のバッグを床に置きっぱなしにしたりせず、
たった数秒の手間を惜しまずに定位置に戻す癖をつけることが、常にきれいなクローゼット、
ひいてはきれいな部屋を維持する一番の近道となります。この小さな習慣の積み重ねが、大きな差を生み、快適な暮らしへと繋がっていくはずです。
7.まとめ:すっきりしたクローゼットで、心に余裕のある暮らしを始めよう
これまでお伝えしてきたクローゼットや押し入れの整理術は、単に物を減らすことが目的ではありません。
物が散らかって片付かないという悩みを解消し、心から満足できる快適な空間を手に入れるためのステップです。
この記事では、まず理想のクローゼットを具体的にイメージする「準備」から始め、次に「必要」「不要」「保留」に仕分ける「断捨離」の実践、そしてリバウンドしないための「収納」テクニック、
最後にきれいな状態を維持する「習慣化」のコツまで、一連の流れを詳しくご紹介してきました。
これらのステップを実践することで、クローゼットがすっきりするだけでなく、探し物の時間がなくなり毎日の生活にゆとりが生まれます。
また、本当に必要なもの、大切なものだけが残ることで、無駄な買い物が減り経済的な余裕も生まれるでしょう。
そして何よりも、整理された空間は、あなたの心にも平穏と安定をもたらしてくれます。
断捨離は、理想の暮らしを手に入れるための素晴らしい手段です。
さあ、あなたも今日から、すっきりとしたクローゼットで、心に余裕のある暮らしを始めてみませんか?
リス公式オンラインショップでは、お部屋を片付けるのに最適な収納ケースを多数
取り揃えております。
ぜひ合わせてご覧くださいね♪







